「ゲイシャ ラーカスタ。ゲイシャ」
日本に行って来たことがあって、日本での体験が忘れられないのか、それとも日本人が目の前にいるから、日本と言えば、、、と日本の噂を聞いて、そんなことを言うのかは不明。
また、フィンランド語での数字の数え方はこうだよ、と後について皆で発音練習だ。(関心の有る方のために次回ちょっとだけご紹介します)
2本目の小ビール瓶が注文された。スウェーデンのたばこ、フィンランドのたばこ、日本のたばこ、とお互いに各国のたばこの国際親善、品評会、お互いにそれぞれの国代表を試してみる。吸い合う。どうだい、美味いかい? 美味い会。
全く別のフィンランド人一人が我々の席の方にやって来て、我々の仲間の誰かに話し掛けるともなしに我々の方に向かって話し出す。我々全員の関心は次第にそのフィンランド人の方へと向かう。この人は英語を話す。でも、この人は何が欲しいのか。
我々が和気藹々とやっていたので、そんな雰囲気についつい惹かれて、話してみたかったのだろうか。一緒に飲んでうきうき気分になり、暫しの幸せを掴みたかったのだろう。
団体旅行の予定にはなかった、駅構内での国際交流、第一部、まずは成功裏に終わった。
■タクシーでYHにやってくると、、
我々はタクシーを拾って、YHがあるスタジアムまでやって来る。と、YHは閉まっている。「月曜日は閉まっているよ」とタクシーの運転手は教えてくれる。
YHに一旦荷物を預けた後、「東京」というバーに行くことになっていた。さて、どうしようか。荷物は何処に持って行こうか。二人はその場に残り、三人はタクシーに乗って、そのバーへと行く。
■日本式レストランで
バーの中。店内は暗い。ヘルシンキ市内、日本式レストランはここ一店しかないという。日本のお酒が注文された。英語が曲がりなりにも話せるのはヒロだけと言ってよいだろう。
ヒロと英語を話すフィンランド人との間で話が交されたが、会話は途切れがち。明るかった駅構内とは違って、ここは暗く会話が弾まないような雰囲気になっているみたいだ。酒の種類も違う。
初対面の、そのフィンランド人、今日は会社が休みで、定期を買いに来たのだそうだ。我々がフィンランドにやって来て、駅構内の一角でその人を言わば待っていたとは夢にも思わなかっただろう。遙か遠くからやって来た我々日本人に対するそのフィンランド人の親愛感が感じ取れる。
次にはウオッツカの炭酸割が運ばれてきた。
飲んだ。
飲んだぞ。おお〜!
頭がクラクラする。頭が泳いでいるのか、それが分かる。おお、直ぐに酔っぱらってしまった。凄い、強い酒だ。
「Good boys! Good boys!」
お酒の影響か、舌が回らないとでも言うのか、話が時々途切れる。話す話題を一つ一つ探し出してきては喋るといった按配であった。その途切れた合間を埋めるかのように、そのフィンランド人は我々に向かって口癖のように繰り返す。
「Good boys! Good boys!」
君たちは立派だ。褒め言葉であることは分かるのだが、何処が、何が、そんなに goodなのか。ヒロに関する限り、よく分からなかった。
■YHへと戻ると、、、
暫し酔っぱらったまま、酔いを醒ますためにも、スタジアムまで歩いて行く。と、何だ、YHは開いていた! 今日は火曜日ではないか。
受付を済ませた後、我々は海を見る目的でヘルシンキの街を歩いていた。何処を歩いているのだろうか。腹も減ってきた。帰ろう、帰ろう。店は閉まっているし。
YH内でのこと。とにかく、泊まることは出来た。今までの仲間が一緒である。各国の若者達も泊まっている。耳に聞こえてくるのは殆どドイツ語だ。
我々の自意識過剰とでもいえようか、何となく感じられたこと、それは多くの目が、奇異の目とでも言えようか、好奇の目とでもいうのか、そんな目が我々に注がれていたということだ。やはり、日本人の集団
、団体さんというのは目立つらしい。
午後8時を過ぎても、外はまだ明るい。真夜中の12時を過ぎてもまだ何となく明るい。尤もそのころには次第に暗くなって行ったのだが、所謂白夜が見られるのであった。
■リスニングの練習?
別のロビーでヒロは外国人の若者達の話し合いに参加していた。長ソファーに腰を降ろして、耳を側立てていただけのことだったが、話していることが分かるものなのかどうなのかと自分をテストしていたとも言える。
左隣に腰掛けていたドイツ人女性が、「ちょっと鉛筆を貸してくれ」と英語で話し掛けてきた。その隣のアメリカ人は良く喋るわ。喋ること、喋ること。法螺を吹きっぱなしだ。
ジョークともいうのか。ヒロは彼等達が喋っているのを殆ど聞いているだけであった。尤も自分では積極的に話し合いに参加しているつもりであった。
彼等達の話している内容はほぼ理解できる。が、こちらから、自分からその内容に関連した英語が思うように出てこない。話の輪に加われない。これはショックであった。
タイミングがつかめない。もどかしい。要するに、英語会話、というか英語のディスカッションに慣れていないのだから仕方ない、と言えばそうかもしれない。どうしようもない。耳が慣れて、口が慣れるまで待つしかないのだろう。考えながら喋るのか、喋りながら考えるのか、考える余裕を自分に与えていると、もう言葉は発せられず、会話の流れについて行けない。遅れてしまっている。頭の中で和文英訳をやっている暇などはない。自動的に口から言葉
が出てこないと会話は会話とならないのだ。とは言え、何も考えずにいわば出任せ的に英語を、日本語を喋るが如くに流暢に出て来るのか、というのでもない。
人を惹きつけるような話題に乏しい。これが問題なのだ。内心、英語がちょっとばかり出来ると自負したり自慢している愚かさ。現実にぶつかってそんな矜持も木っ端みじんに砕けてしまった。少しぐらい聞けたり話せたりだけでは駄目、もっと何かプラスアルファが必要と痛感させられた。実力のなさ、背伸びをしても、宙返りをしたとしても、どうしようもない、そんな絶望感に
ちょっと襲われてしまった。怖ろしい。もっともっと勉強しなければならない。自分一人、全身耳にしながらも心の内では猛省していた。もうしょうがないなあ、と。
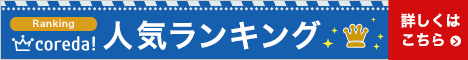
■世界の若者との交流への目覚め
とにかく、我々は夜遅くまで、話し合っていた。我々はお互いに世界の若者同士だという意識を、少なくともヒロは持ちながら、その長ソファーに粘っていた。
翌日の午前1時30分を過ぎていた。眠たいのを我慢して、そのソファーの中に留まっているのも、そろそろ限界だと感じていた。実は途中で席を立ってしまうことを、何故か恐れていたとも言えようか。自分一人その場から離れて行ってしまうことに何か世界各国からの若者が集う国際交流の場から自分で一方的に背を向けてしまうかのように思われて、その場にいつまでも腰掛けていた。
そこに屯していた人たちが何を話しているのかも時には分からなくなってしまう、それでも話の筋を辿って行こうと耳を緊張させ側立てていたが、明日からは自分一人だけでのヒッチハイクの旅が始まるという思いが脳裏の隅にあった。